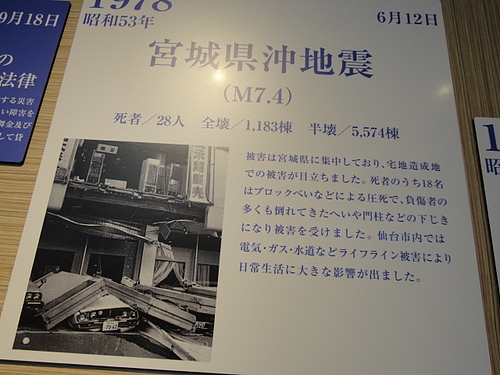暑い日が続いておりますね。熱中症に注意ですね。歩いていて足がほつれたりしたら、それは熱中症のサインだとか。睡眠中にも熱中症になることがあるので寝る前に水分を取るとよいそうです。以下、僕がテレビで知った情報ですw
今日は、曲名に「青」がつく曲のアンケートです。曲名に赤とか白とか青とか色がつく楽曲は、それこそ色々ありますが、とりわけ「青」は非常に多い。青は日本人が好きな色のひとつなのかもしれない。実際、日本人が好きな色のランキングで「青」は二位に入っております。ちなみに一位は「黒」だそうです。意外ですね。ブラック企業とか、黒星とか良くない意味で使われたり、今のこの時期に台所とかでゴソゴソ出てくるGの色も黒なので、むしろ嫌いな色にランキングされそうなのに。
万葉集にも「あをによし、奈良の都は、咲く花の、にほふがごとく、今盛りなり」とあります。意味は「奈良の都は花の香が香ばしく、今が盛りとたくさん咲いています」。「あをに」とは漢字で「青丹」と書きまして、「あをによし」は「奈良」にかかる枕詞です。青丹は青色の土のことで、奈良では「青丹」がよく取れたのですね。おもに顔料や化粧料の黛に使われたそうです。青丹とは僕も実物を見たことがないのですが、その色は青とはいいがたく緑色に近いそうですが。
今日は、曲名に「青」がつく曲のアンケートです。曲名に赤とか白とか青とか色がつく楽曲は、それこそ色々ありますが、とりわけ「青」は非常に多い。青は日本人が好きな色のひとつなのかもしれない。実際、日本人が好きな色のランキングで「青」は二位に入っております。ちなみに一位は「黒」だそうです。意外ですね。ブラック企業とか、黒星とか良くない意味で使われたり、今のこの時期に台所とかでゴソゴソ出てくるGの色も黒なので、むしろ嫌いな色にランキングされそうなのに。
万葉集にも「あをによし、奈良の都は、咲く花の、にほふがごとく、今盛りなり」とあります。意味は「奈良の都は花の香が香ばしく、今が盛りとたくさん咲いています」。「あをに」とは漢字で「青丹」と書きまして、「あをによし」は「奈良」にかかる枕詞です。青丹は青色の土のことで、奈良では「青丹」がよく取れたのですね。おもに顔料や化粧料の黛に使われたそうです。青丹とは僕も実物を見たことがないのですが、その色は青とはいいがたく緑色に近いそうですが。